【基本編】おせちの取り分け方と箸使いのマナー全手順
新しい年の幕開けを祝う、華やかなおせち料理。ご家族や大切な方々と囲む食卓は、格別な時間ですよね。しかし、特にパートナーの実家など、目上の方がいる席では「取り分け方やマナーはこれで合っているだろうか…」と、ふとした瞬間に不安を感じることはありませんか?その一瞬の迷いが、せっかくの楽しいお正月の雰囲気に水を差してしまうことも。
でも、もうご安心ください。実は、おせちの取り分け方は、たった一つの「思いやりの心」という原則と、これからご紹介する具体的な手順さえ押さえれば、決して難しいものではありません。この記事を最後まで読めば、あなたは自信を持って、誰よりも美しく、そしてスマートにおせちを取り分けることができるようになります。「育ちの良い、気の利く人だ」と、周りからの評価もきっと上がるはずです。さあ、一緒に完璧なマナーをマスターしていきましょう。
すべての基本!おせちを取り分ける前の心構えと「器」の準備
おせちの取り分けマナーの根幹にあるのは、「神様と共に祝い、集う人々で福を分かち合う」という精神です。これから行う一つ一つの所作は、この精神を形にしたものだと理解すると、自然と美しい振る舞いにつながります。技術的な手順に入る前に、まずはこの心構えと、最低限必要な「器」の準備について確認しましょう。
- 心構え:おせちは「芸術品」と心得る
お重に詰められたおせちは、料理人や作り手が時間と心を込めて作り上げた、新春を祝う芸術品です。取り分ける際は、その美しい盛り付けをいきなり崩してしまわないよう、細心の注意を払うことが最も重要です。全体のバランスを見ながら、どこから取れば美しさを保てるかを一瞬考える、その心遣いが品格となって表れます。 - 器の準備①:取り皿(銘々皿)
おせちをいただく際は、必ず各自に取り皿を用意します。お重から直接自分の口に運ぶのはマナー違反です。懐紙(かいし)があればそれでも構いませんが、ご家庭では小ぶりの美しいお皿を用意すると良いでしょう。これがあるだけで、食卓がより一層華やかになります。 - 器の準備②:取り箸
おせちを取り分ける際には、必ず「取り箸(とりばし)」を使いましょう。自分の口をつけた箸で大皿の料理に触れる「直箸(じかばし)」は、衛生的な観点からも絶対に避けなければならないマナー違反の筆頭です。お重ごとに専用の取り箸が用意されているのが理想ですが、ない場合はホスト(おもてなしする側)に「取り箸をいただけますでしょうか?」と一声かけるのがスマートです。もし、どうしても取り箸が見当たらない場合の緊急対処法については、後ほど詳しく解説します。
決定版!おせちの取り分け「美しい3ステップ手順」
心構えと準備が整ったら、いよいよ実践です。ここからは、席に着いてから実際に取り分けるまでの一連の流れを、具体的な3つのステップに分けて徹底解説します。この手順通りに行えば、あなたの所作は驚くほど洗練されます。
ステップ1:どこから取る?重箱の順番と基本ルール
おせち料理が詰められたお重は、上から「一の重」「二の重」「三の重」と続きます(四段の場合は「与の重」)。取り分ける際は、必ず一番上のお重から手をつけるのがマナーです。下のお重から先に取るのは、美しい盛り付けを崩すだけでなく、全体の構成を無視する行為と見なされます。
- 原則①:上段から下段へ
まずは最上段である「一の重」に詰められた祝い肴や口取りから取り始めます。一の重の料理がある程度減ってきたら、次に「二の重」の焼き物や酢の物、そして「三の重」の煮物へと進んでいくのが正式な流れです。 - 原則②:左上から奥へ、そして手前へ
お重の中の料理を取る順番にも、美しさを保つための暗黙のルールが存在します。基本は、お重の左上にある料理から取り始め、奥へと進み、その後手前の料理へと移っていきます。これは、盛り付けの中心や手前にある料理をいきなり取ることで、全体のバランスが大きく崩れるのを防ぐための知恵です。山のものを少しずつ崩していくようなイメージを持つと分かりやすいでしょう。
ステップ2:どう取る?「取り箸」と「祝い箸」の正しい使い方
取り箸を手に取ったら、いよいよ料理をお皿に移します。ここで重要になるのが「箸使い」です。特に、お正月に使われる「祝い箸」には特別な意味があるため、その使い方を正しく理解しておく必要があります。
- 取り箸の正しい使い方
取り箸を使い、お重から料理を静かに取ります。一度にたくさんの量を取ろうとせず、食べきれる分だけを品よく取ることが大切です。汁気のあるものは、他の料理につかないようにそっと器の縁で汁気を切ってからお皿に移しましょう。 - 「祝い箸」とは?
祝い箸は、柳の木で作られた両端が細くなっているお箸で、「両口箸(りょうくちばし)」とも呼ばれます。この箸の片方は人間が使い、もう片方は神様が使うとされています。つまり、祝い箸は食事を通じて神様と繋がるための、非常に神聖な道具なのです。そのため、この祝い箸を取り箸の代わりとして使う際には、特別な注意が必要となります。
ステップ3:どう置く?取り分けたおせちの美しい盛り付け方
ただお皿に乗せるだけでなく、美しく盛り付けることで、おせち料理はさらに美味しく感じられます。ここでの少しの工夫が、あなたのセンスの見せどころです。
- 量のマナー:全種類を少しずつ
取り皿には、たくさんの種類を少しずつ盛り付けるのが基本です。一つの料理を大量に取って自分のお皿を山盛りにしてしまうのは、卑しい印象を与えかねません。周りの人が全ての料理を十分に楽しめるよう、配慮の心を持つことが大切です。苦手なものまで無理に取る必要はありませんが、彩りを考えて数種類を上品に盛り付けましょう。 - 空間を活かす「余白の美」
お皿いっぱいにぎゅうぎゅうに詰めるのではなく、余白を活かして盛り付けましょう。料理同士がくっつかないように少し間隔をあけ、高低差をつけると立体感が出て美しく見えます。例えば、黒豆のような黒い色の隣には、紅白なますのような明るい色を配置するなど、彩りを意識すると、まるでお店の前菜のような一皿が完成します。
【緊急事態】取り箸がない!そんな時のスマートな対処法
さて、ここが最も多くの人が迷うポイントかもしれません。親戚の集まりなど、カジュアルな場では取り箸が用意されていないケースも少なくありません。そんな時、あなたならどうしますか?「直箸」は論外ですが、「逆さ箸」も実はマナー違反。ここでは、そんな緊急事態を乗り切るためのスマートな対処法を伝授します。
最も確実で丁寧な方法は、その家のホスト(おもてなし役)に「恐れ入ります、お取り箸をいただけますでしょうか?」とお願いすることです。これが一番角が立たず、マナーを心得ているという印象も与えられます。
ホストにお願いしにくい状況や、すぐに取り箸が出てこない場合は、自分の祝い箸で代用します。ただし、絶対に自分の口をつけた側を使ってはいけません。前述の通り、祝い箸の片方は神様のためのものです。まだ一度も使っていない、清浄な神様側の箸先を使って、料理を取り分けます。この際、指が箸先に触れないよう、箸の中央を清潔な懐紙やティッシュで持って行うと、より衛生的で丁寧な印象になります。
「自分の箸を逆さに持って使えば、口をつけていないから大丈夫」と考える「逆さ箸」。これは一見、合理的に見えますが、実は重大なマナー違反です。理由は二つあります。
- 衛生的な理由:箸の上部は、自分の手が直接触れている部分です。その手で触れた部分を、みんなが食べる神聖な料理に入れることは、衛生的とは言えません。
- 文化的な理由:「一度下にしたもの(手で持つ側)を、上(料理側)に向ける」という行為が、縁起が悪い、神様に対して失礼にあたると考えられています。
逆さ箸は、「マナーを知らない人」という印象を与えてしまう可能性が非常に高い行為です。必ず避けるようにしましょう。
これだけは避けたい!一発で品格が疑われるNG箸使いワースト5
おせちの席に限らず、和食の席では「嫌い箸(きらいばし)」または「忌み箸(いみばし)」と呼ばれる箸使いのタブーが存在します。無意識にやってしまうと、想像以上に悪い印象を与えてしまいます。ここでは代表的なものを5つご紹介します。これらを避けるだけで、あなたの所作は格段に美しくなります。
刺し箸(さしばし)
料理に箸を突き刺して取ること。特に煮物など、滑りやすいものを取る際にやってしまいがちですが、「食べ物を道具で刺す」という行為は非常に品がなく見えます。
迷い箸(まよいばし)
どの料理を取ろうか迷って、料理の上で箸をあちこち動かすこと。「優柔不断」「食べ物への感謝がない」と見なされます。取る料理は、箸を伸ばす前に心の中で決めましょう。
寄せ箸(よせばし)
遠くにある器を、箸を使って手元に引き寄せること。面倒くさがっているように見え、行儀が悪い行為の代表格です。必ず手で器を持ちましょう。
涙箸(なみだばし)
料理の汁などを、箸先からポタポタと垂らしながら口に運ぶこと。テーブルやお皿の周りを汚してしまい、見た目にも美しくありません。取り皿や手で受けながら運ぶ「手皿」も実はマナー違反なので、汁気は器の縁で軽く切ってから運びましょう。
舐り箸(ねぶりばし)
箸についた食べかすなどを、舐めとること。言うまでもなく、非常に見苦しい行為です。子供っぽい印象を与えてしまうので絶対にやめましょう。
あなたのマナーは完璧?おせちの取り分け習熟度チェックリスト
お疲れ様でした。ここまでで、おせちの取り分けに関する知識は完璧になったはずです。最後に、これまで学んだことをいつでも思い出せるように、チェックリスト形式の表にまとめました。お正月を迎える前に、また、おせちをいただく直前に、このリストを見返してみてください。この表の内容がすべて「OK」になっていれば、あなたはもう、どこに行っても恥ずかしことのない「おせちマナーの達人」です。ぜひブックマークしてご活用ください。
| チェック項目 | OK例(具体的な行動) | NG例(具体的な行動) | なぜ?(理由とポイント) |
|---|---|---|---|
| 【心構え・準備】 取り分けの精神を理解しているか? |
「福を分かち合う」という気持ちで、美しい盛り付けを崩さないよう配慮する。 | 自分の食べたいものから、全体のバランスを考えずに取る。 | おせちは新年の神様への感謝と祝いの気持ちを表すものです。作り手と、同席者への敬意が基本です。 |
| 【取り始めの作法】 正しい順番で手をつけているか? |
一番上のお重の、左上奥から取り始める。 | 下のお重から取る。真ん中から取る。 | 全体の美しい盛り付けをできるだけ長く保ち、物語に沿って料理をいただくという作法です。 |
| 【箸の使い方】 直箸をしていないか? |
必ず専用の「取り箸」を使う。 | 自分の口をつけた箸で、お重の料理を取る。 | 同席者への配慮と衛生観念の基本中の基本です。 |
| 【緊急時の対応】 取り箸がない場合に正しく対処できるか? |
ホストに頼むか、自分の祝い箸の「神様側(未使用側)」を使う。 | 逆さ箸(そらばし)で取る。 | 逆さ箸は、手が触れた部分で料理に触れるため不衛生であり、縁起も悪いとされるためです。 |
| 【盛り付けの美学】 品の良い盛り付けができているか? |
多くの種類を少しずつ、彩りや余白を意識して盛り付ける。 | 好きなものだけを大量に取る。お皿に山盛りにする。 | 「分かち合う」精神の表れです。欲張らず、上品にいただくのが美しい作法です。 |
| 【嫌い箸の回避】 NGな箸使いを避けているか? |
料理を箸で刺したり、箸で器を寄せたりしない。 | 刺し箸、迷い箸、寄せ箸など無意識に行う。 | これらは古くからの食事作法のタブーであり、品格や育ちが表れるポイントです。 |

【応用編】シーン別で見るおせちの取り分けマナー
基本編で、おせちの取り分け方と箸使いの「型」をマスターしたあなた。しかし、本当の上級者とは、その「型」を状況に応じてしなやかに使いこなせる人のことを指します。例えば、気心知れた友人との集まりと、パートナーの実家での新年会とでは、求められる立ち居振る舞いのレベルが全く異なるのは想像に難くないでしょう。せっかく身につけた知識も、場面に合っていなければ「堅苦しい人」「空気が読めない人」と、かえってマイナスの印象を与えかねません。
この応用編では、あなたが遭遇するであろう具体的な4つのシーンを想定し、それぞれで「何をどこまで意識すれば良いのか」「どう振る舞えば最も好印象を与えられるのか」を徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたはどんな状況でも臆することなく、自信に満ち溢れた立ち居振る舞いができるようになっているはずです。マナーを単なる作法から、あなたの評価を上げるための強力なコミュニケーションツールへと昇華させましょう。
【緊張度MAX】パートナーの実家・親戚の集まりでの鉄壁マナー
お正月における最大の難関とも言えるのが、パートナーの実家や親戚一同が集まる席ではないでしょうか。「常識のある、素敵な人だと思われたい」その一心で、普段以上に気を遣い、疲れてしまう方も少なくありません。しかし、ポイントさえ押さえれば、ここはあなたの評価を最大限に高める絶好のチャンス。大切なのは「感謝と尊敬の気持ちを行動で示す」ことです。ここでは、具体的な行動レベルでの鉄壁のマナーをご紹介します。
- 最重要ポイント①:手伝いを申し出るタイミングと美しい断られ方
席に着く前、台所が忙しそうなタイミングで「何かお手伝いできることはありますか?」と声をかけるのが基本です。この一言があるかないかで、第一印象は大きく変わります。もし「大丈夫よ、座っていて」と断られた場合も、食い下がってはいけません。「ありがとうございます。では、お言葉に甘えさせていただきます」と笑顔で引き下がり、その代わりにお皿を運んだり、食後には率先して片付けを手伝うなど、別の形で感謝の気持ちを示しましょう。この「引き際の美しさ」が、デキる大人の証明です。 - 最重要ポイント②:お酌の順番と目配り
お酌をする際は、まず上座に座っている年長者から順番に行うのがマナーです。パートナーの両親、祖父母、そして他の親戚の方々へと続きます。誰か一人のグラスが空になるのを待つのではなく、全体のグラスの減り具合に常に気を配り、「〇〇さん、次は何を飲まれますか?」と声をかける気配りが喜ばれます。 - 最重要ポイント③:子供への対応
親戚に子供がいる場合は、その子への対応も重要なマナーの一部です。子供が騒がしくしても嫌な顔一つせず、笑顔で見守る姿勢が大切です。「〇〇ちゃん、伊達巻は甘くて美味しいよ」などと、子供の目線で話しかけてあげると、親からの好感度も格段にアップします。自分の子供のマナーを教える良い機会と捉え、取り分け方を優しく教えてあげるのも素晴らしい振る舞いです。
<こんな時はどうする? Q&A>
パートナーの実家に、独自のルールがある場合はどうすれば?
A. その家のルールに敬意を払い、素直に従うのが最善です。例えば、お重から直箸で取るのが慣習だったとしても、それを真っ向から否定してはいけません。「郷に入っては郷に従え」です。ただし、衛生面が気になる場合は「皆様のお箸が汚れてしまいますので、よろしければこちらのお箸をお使いください」と、新しい取り箸をそっと差し出すなど、相手を立てつつスマートに提案できると理想的です。
【評価が決まる】ビジネスの会食・目上の方をもてなす席での作法
ビジネスシーンでのおせち料理は、単なる食事ではなく、あなたの社会人としての品格や教養が試される「テスト」の場でもあります。ここでの振る舞い一つで、仕事の評価が左右されることも。パートナーの実家とはまた違う、フォーマルな緊張感が漂うこの場面では、「敬意と礼節を重んじた、無駄のない所作」が求められます。
- 最重要ポイント①:上座・下座の絶対厳守
和室・洋室を問わず、入り口から最も遠い席が「上座」です。役職が最も高い人が上座に着くのが基本なので、自分は入り口に近い「下座」に座るのが鉄則。もし席を勧められた場合でも、「とんでもないです。私はこちらで結構でございます」と一度は謙遜する姿勢を見せましょう。 - 最重要ポイント②:スマートな「取り計らい」
自分がお重から遠い下座にいる場合、無理に手を伸ばすのは見苦しい行為です。近くに座っている人に「恐れ入りますが、そちらの海老をお取りいただけますでしょうか」と丁寧にお願いしましょう。逆に、自分がお重の近くにいる場合は、上座の人が取りやすいように「〇〇部長、よろしければお取りいたしましょうか?」と一声かけ、お重の蓋を開けたり、取りやすいように向きを変えたりする配慮ができると、「気が利く人物」という評価に繋がります。 - 最重要ポイント③:会話を止めない料理の知識
ビジネスの席では、沈黙は避けたいもの。「この黒豆は『まめに働く』、数の子は『子孫繁栄』の願いが込められているそうですね」といった、おせち料理のいわれや意味に関する知識は、会話のきっかけとして非常に役立ちます。ただ食べるだけでなく、料理にまつわるうんちくを少し披露できると、あなたの教養の深さを示すことができます。
<こんな時はどうする? Q&A>
大事な話の最中や、会話が途切れてしまったら?
A. 会話がメインの場では、黙々と食べることに集中しすぎないよう注意が必要です。話が重要な局面に入ったら、一度箸を箸置きに置き、相手の目を見て話を聞くことに集中しましょう。もし会話が途切れたら、前述の料理の知識を披露するチャンスです。「こちらの伊達巻は、巻物に似ていることから知識が増えることを願う縁起物だそうですよ」といった一言が、場の空気を和ませ、次の会話へと繋げてくれます。
【視点を変える】あなたがホスト(もてなす側)になった時の心配り
これまではゲストとしてのマナーを見てきましたが、今度はあなたが誰かを自宅に招き、おせちを振る舞う「ホスト側」の立場になった場合のマナーです。最高のホストとは、ゲストに一切の気遣いをさせず、心からお正月を楽しんでもらう空間を作り出せる人。ここでのキーワードは「究極の先読みと、おもてなしの心」です。
- 最重要ポイント①:完璧な「道具」の準備
ゲストが「取り箸はありますか?」と聞く必要がないよう、お重の段ごとに一本ずつ、あるいは大皿ごとに一本ずつ、あらかじめ美しい取り箸を添えておきましょう。取り皿も、少し多めに用意しておくと、途中で汚れた際に交換できて親切です。料理だけでなく、こうした道具の準備にこそ、ホストの品格は表れます。 - 最重要ポイント②:アレルギーや苦手な食材への配慮
ゲストを招くことが決まったら、事前に「何かアレルギーや苦手な食べ物はありませんか?」と確認しておくのが、現代の必須マナーです。特に甲殻類(海老など)や卵は、おせちによく使われるアレルゲンです。もしアレルギーを持つゲストがいる場合は、その人が食べられる料理を別皿で用意したり、「このお料理には〇〇が入っています」と書いた小さな札(ふだ)を添えておくと、非常に丁寧で安心感を与えられます。 - 最重要ポイント③:場の空気を作る「声かけ」
「皆様、どうぞお箸をお取りください」「これは私が作った煮物です、お口に合うと嬉しいのですが」といったホストからの一言が、ゲストが食事を始めるきっかけとなり、場の空気を和ませます。「どうぞ、お重が崩れるのを気にせず、好きなものからたくさん召し上がってくださいね」と最初に伝えることで、ゲストの心理的な負担を大きく減らすことができます。
<こんな時はどうする? Q&A>
ゲストが明らかなマナー違反をしてしまったら?
A. ホストの最大の役割は、その場を楽しく保つことです。ゲストのマナー違反を直接指摘するのは、場の空気を凍らせてしまう最悪の対応です。たとえ直箸をされたとしても、見て見ぬふりをするのが大人の対応。その人が箸を置いたタイミングで、何事もなかったかのようにそっと新しい取り箸と交換しておく、くらいの心遣いができれば完璧なホストと言えるでしょう。
【気楽に楽しむ】友人とのホームパーティーでの“やりすぎない”マナー
親しい友人同士で集まるカジュアルなパーティーでは、これまでのフォーマルなマナーをそのまま持ち込むと、かえって浮いてしまう可能性があります。ここでは、親しき中にも礼儀あり、という絶妙なバランス感覚、いわば「場を白けさせない、柔軟なマナー」が求められます。
- 最重要ポイント①:ホストに気を使わせない手土産
友人宅への手土産は、高価すぎるものは避けましょう。相手にお返しを考えさせてしまうような品はNGです。みんなで楽しめる少し珍しいお酒や、食後のデザートになるようなスイーツなどが最適です。「これ、よかったらみんなで飲もう(食べよう)!」と、その場で開けることを前提に渡すと、ホストの負担になりません。 - 最重要ポイント②:「取り箸、どうする?」の確認
もし取り箸が用意されていない場合、いきなり自分の箸の神様側を使うのではなく、「ねえ、取り箸ってどうする?気にしない感じ?」と、まずはホストや周りの友人に一声かけてみましょう。この一言で、場のルールを確認しつつ、自分はマナーを意識しているということもさりげなく伝えられます。「あ、ごめん忘れてた!」となれば取り箸が出てくるでしょうし、「もう気にしなーい!直箸でいこう!」となれば、その場の空気に従うのが正解です。 - 最重要ポイント③:「無礼講」の境界線を見極める
いくら気心が知れた仲でも、食べ方が汚かったり、一人で特定の料理を独占したりするのはもちろんNGです。お酒が入ると気が大きくなりがちですが、最低限の「嫌い箸」を避ける意識は持ち続けましょう。「無礼講」とは、何をしても許されるという意味ではなく、「礼儀を少し簡略化して、もっと楽しみましょう」というポジティブな提案なのです。
【完全保存版】ひと目でわかる!シーン別おせちマナー早見表
ここまで、4つの異なるシーンでのマナーを学んできました。最後に、それぞれのシーンで求められる心構えや注意点を一覧できる「早見表」を作成しました。情報が頭の中で整理され、どんな状況でも瞬時に最適な行動が取れるようになります。ぜひこの表をブックマークして、来年のお正月に備えてください。これさえあれば、あなたはもう怖いものなしです。
| シーン | 緊張度レベル | 最重要マインド | 特に注意すべきポイント |
|---|---|---|---|
| パートナーの実家 | ★★★★★ | 感謝・尊敬・気配り | 手伝いの申し出方とタイミング。お酌の順番。子供への対応。その家のルールを尊重する姿勢。 |
| ビジネスの会食 | ★★★★☆ | 敬意・礼節・品格 | 上座・下座の絶対厳守。お重が遠い場合のスマートな依頼。会話を止めないための料理知識。 |
| ホスト(もてなす側) | ★★★☆☆ | おもてなし・先読み | 取り箸や取り皿の十分な準備。アレルギー等の事前確認。ゲストに気を使わせない声かけ。 |
| 友人とのパーティー | ★★☆☆☆ | 楽しむ心・柔軟性 | 場の空気を読むこと。「やりすぎない」マナー。ホストに気を使わせない手土産や手伝いのバランス。 |
ご覧の通り、すべてのシーンに共通しているのは、形式的な作法そのものよりも、根底にある「相手を思いやる心」です。なぜこのマナーがあるのか、その背景を理解すれば、あなたの振る舞いは自然と美しく、そして心からのものになるでしょう。さあ、自信を持って、素晴らしい新年のお祝いの席をお楽しみください。

【知識編】知っておきたいおせち料理の意味と食べる順番
これまでの章で、おせちを取り分ける際の美しい「所作」をマスターしてきました。しかし、その所作に「心」を込めることで、あなたの振る舞いはさらに輝きを増します。おせち料理は、単なる美味しいご馳走の詰め合わせではありません。一つ一つの料理が、先人たちの深い祈りと願いが込められた「言祝ぎ(ことほぎ)のシンボル」であり、お重全体が一つの壮大な「新年の物語」を紡いでいるのです。
この章では、その物語を読み解くための知識、すなわち料理に込められた意味と、その物語を正しく味わうための「食べる順番」について詳しく解説します。この知識は、あなたの食卓での会話を豊かにし、子供たちに日本の素晴らしい文化を伝える際の強力な武器となります。なぜなら、意味を知って食べる一口は、知らないで食べる十口にも勝る深い味わいと感動を与えてくれるからです。さあ、お重という名の玉手箱を開き、新年の幸福を願う物語の世界へ旅立ちましょう。
まず、個々の料理の話に入る前に、おせちが入っている「お重(じゅうばこ)」そのものに込められた意味を理解することが不可欠です。なぜ、おせちはわざわざ重箱に詰められているのでしょうか。
- 「福を重ねる」という願い
重箱が段々に重ねられているのは、「めでたさを重ねる」「幸福を重ねる」という願いを込めた、非常に縁起の良い形式だからです。一段一段、丁寧に福を積み上げていくイメージが、新年の始まりにふさわしいと考えられました。正式な段数は四段重(与の重)ですが、現代では三段重が一般的です。 - 上から下へ食べる「物語」の作法
おせちを上のお重から順番に食べていくのには、明確な理由があります。これは、新年の宴の始まりから終わりまでを表現した、一種の「コース料理」として構成されているためです。- 一の重:年の初めに、神様とお屠蘇を酌み交わすための「祝い肴」と「口取り」
- 二の重:海の幸を中心とした、宴を彩る「焼き物」と「酢の物」
- 三の重:山の幸に感謝し、家族の結びつきを願う「煮物」
お重の最上段、蓋を開けて最初に目に飛び込んでくるのが「一の重」です。ここには、おせちのプロローグとも言うべき、最も重要で神聖な料理が詰められています。主役は「祝い肴三種(いわいざかなさんしゅ)」と呼ばれる、おせちの基本セットです。
- 数の子(かずのこ):子孫繁栄の象徴
ニシンの卵である数の子は、その卵の多さから「子宝に恵まれ、子孫が繁栄しますように」という強い願いが込められています。プチプチとした食感は、生命の力強さを感じさせてくれます。 - 黒豆(くろまめ):無病息災と勤勉の証
「まめ」という言葉には、「真面目に、誠実に」という意味があります。そこから「まめに働き、まめに(健康に)暮らせるように」という願いが込められました。また、黒色は魔除けの色ともされています。 - 田作り(たづくり):五穀豊穣への祈り
カタクチイワシの稚魚を干して飴炊きにしたもの。かつて、イワシを田んぼの肥料にしたところ、米が五万俵も収穫できたという言い伝えから「田作り」と名付けられ、五穀豊穣を願う縁起物となりました。
この三種に加えて、色鮮やかな「口取り(くちとり)」が華を添えます。これらは酒の肴として、宴の始まりを楽しく演出する役割を担っています。
- 伊達巻(だてまき):学問成就と華やかさ
形が巻物に似ていることから、「知識が増え、学問や習い事が成就しますように」という願いが込められています。また、派手で見栄えが良いことから、伊達者(だてもの)の着る派手な着物の反物を連想させ、華やかさを象徴します。 - 紅白かまぼこ(こうはくかまぼこ):祝祭と魔除け
半円の形は「初日の出」を象徴しています。また、赤色は「魔除け」、白色は「神聖・清浄」を意味し、紅白の組み合わせは日本における祝祭の基本カラーです。 - 栗きんとん(くりきんとん):金運と勝負運
「きんとん」は漢字で「金団」と書き、金の団子、すなわち財宝を意味します。その黄金色から、豊かな一年と商売繁盛、金運の上昇を願う料理です。また、栗は「勝ち栗」とも言われ、勝負運向上の縁起物でもあります。
物語が中盤に差し掛かる「二の重」。ここには、縁起の良い海の幸を中心とした豪華な「焼き物」と、口の中をさっぱりとさせてくれる名脇役「酢の物」が詰められています。宴の彩りと楽しさが、一気に増す段です。
- 鰤の照り焼き(ぶりのてりやき):立身出世の願い
鰤は、成長するにつれて名前が変わる「出世魚」の代表格です。ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリと成長することから、「将来の立身出世」を願って食べられます。特にお子さんやお父さんの出世を願う家庭では欠かせません。 - 海老の旨煮(えびのうまに):長寿のシンボル
海老は、長いひげを持ち、腰が曲がっている姿から「腰が曲がるまで長生きできますように」という長寿の願いが込められています。また、鮮やかな赤色は魔除けの意味も持ちます。 - 鯛の姿焼き(たいのすがたやき):万能の「めでたい」魚
「たい」という音が「めでたい」に通じることから、お祝いの席には欠かせない魚です。七福神の恵比寿様が持つ魚としても知られ、商売繁盛の縁起物でもあります。 - 紅白なます(こうはくなます):平和と平安の祈り
お祝いの水引をかたどったとされる、紅白の彩りが美しい酢の物です。大根と人参が地に根を張る根菜であることから、「家の土台がしっかりし、家族が平和に暮らせますように」という願いが込められています。
物語のクライマックス、そしてフィナーレを飾るのが「三の重」です。ここには、里芋やれんこん、ごぼうなど、大地で育った山の幸を一つの鍋で煮込んだ「煮物(煮しめ)」が詰められます。様々な具材が一緒に煮込まれる様子を家族に見立て、「家族が末永く仲良く、結ばれていきますように」という、最も心温まる願いが込められています。
- 里芋(さといも):子宝に恵まれる
親芋の周りにたくさんの子芋がつくことから、子孫繁栄の象徴とされています。 - 蓮根(れんこん):将来の見通しが良くなる
たくさんの穴が開いていることから、「将来を良く見通せるように」という願いが込められています。 - ごぼう:家の安泰と豊作
地中深くまでまっすぐ根を張る姿から、「家の土台がしっかり安泰であるように」「根を張って暮らせるように」という願いや、豊作を祈る意味があります。 - 昆布巻き(こぶまき):喜びと子孫繁栄
「こぶ」が「よろこぶ」に通じることから、お祝いの食材として用いられます。「子生婦(こんぶ)」という字をあてて、子孫繁栄を願う意味もあります。 - 椎茸(しいたけ):元気・健康の象徴
亀の甲羅に見立てた飾り切りをすることが多く、亀が長寿の象徴であることから、「家族みんなが元気でいられますように」という願いが込められています。
これまでに紹介した料理の意味を、いつでも見返せるように一覧表にまとめました。さらに、お正月の食卓で披露すれば「物知り!」と感心されること間違いなしの「会話が弾むうんちく」も加えました。このテーブルをスマートフォンに保存しておけば、あなたもおせち博士です。ぜひ、ご家族や親戚との会話を盛り上げるためにご活用ください。
| お重 / 種類 | 代表的な料理 | 込められた願い・意味 | 会話が弾むうんちく |
|---|---|---|---|
| 一の重 (祝い肴) |
数の子 | 子孫繁栄 | 昔は音の良さから「二親(にしん)の子」と言われ、両親の健康も願う意味があったそうです。 |
| 黒豆 | 無病息災・勤勉 | シワが寄らないようにふっくらと煮るのは「シワが寄るまで長生きできるように」という逆説的な願いからです。 | |
| 田作り | 五穀豊穣 | 別名「ごまめ(五万米)」。小さいけれど栄養価が非常に高く、昔の人の知恵が詰まっています。 | |
| 一の重 (口取り) |
伊達巻 | 学問成就・華やかさ | 長崎から江戸に伝わった「カステラかまぼこ」が原型。おしゃれな伊達者たちが好んだとか。 |
| 栗きんとん | 金運上昇・勝負運 | きんとんの色を出すクチナシの実は、漢方薬としても使われる縁起の良い植物です。 | |
| 紅白かまぼこ | 祝祭・魔除け | 板についているのは、昔、魚のすり身を板に塗って焼いていた名残。板は鮮度を保つ役割もあります。 | |
| 二の重 (焼き物) |
鰤の照り焼き | 立身出世 | 関西では鰤、関東では鮭を入れるなど、地域によって出世を願う魚が違うのも面白いですね。 |
| 海老の旨煮 | 長寿 | 海老は脱皮を繰り返して成長することから、「生まれ変わり」や「若返り」の象徴でもあります。 | |
| 二の重 (酢の物) |
紅白なます | 平和・平安 | 生魚を使った「なます」が原型ですが、日持ちするように火を通さない酢の物に変化しました。 |
| 三の重 (煮物) |
蓮根 | 将来の見通し | 仏教では、泥の中から美しい花を咲かせる蓮は、極楽浄土の象徴とされ、神聖な植物です。 |
| ごぼう | 家の安泰・豊作 | たたきごぼうは、開運を祈って叩く「縁起の音」と、身を開いて福を呼び込む意味があります。 | |
| 昆布巻き | 喜び・子孫繁栄 | 中の具材が「にしん(二親)」だと子孫繁栄、「たら(鱈)」だとお腹いっぱい食べられるように、と意味が加わります。 |
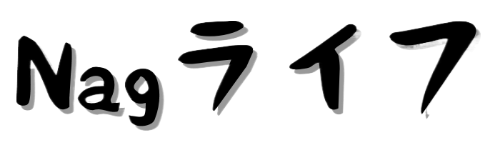



コメント