ハムスターが巣作りしない主な原因5選【環境・ストレス・病気】
大切なハムスターが巣作りをしないのは心配ですよね。でも大丈夫。原因は一つひとつ紐解けば見えてきます。下のボタンから気になる項目を選んで、あなたの小さな家族が送るサインの謎を一緒に解き明かしていきましょう。
【原因1】巣材や巣箱が気に入らない!「住まい」のミスマッチ
ハムスターが巣作りをしない最も一般的で、かつ解決しやすい原因が「住まい」、つまり巣材や巣箱そのものに対する不満です。人間にも寝具や部屋の好みのがあるように、ハムスターにも個体差があり、素材や広さ、形状に強いこだわりを持っていることがあります。
-
巣材の好みと量:
まずチェックしたいのが巣材です。「巣材」とは、ハムスターが巣箱に運び込んでベッドにする材料のこと。一般的にはウッドチップやペーパーチップが使われますが、ハムスターによっては特定の素材を好まなかったり、アレルギーを持っていたりすることもあります。 例えば、針葉樹のウッドチップはアレルギーを引き起こす可能性が指摘されることもあり、その場合は低刺激性の広葉樹のものや、紙製のペーパーチップに変えるだけで劇的に巣作りを始めることがあります。 また、巣材の量が不足していると、そもそも巣作りができません。ハムスターが自分で潜って形を作れるよう、ケージの床から3~5cmほどの深さまでたっぷりと敷いてあげましょう。 -
巣箱の形状・サイズ・素材:
巣箱自体も重要なチェックポイントです。巣箱がハムスターの体に対して大きすぎると落ち着かず、逆に小さすぎると窮屈で入りたがりません。 目安としては、ハムスターが3匹ほど入れるくらいの広さが理想的とされています。 素材も木製、陶器製、プラスチック製と様々ですが、かじり癖のある子には安全な木製、夏場の暑さ対策にはひんやりとした陶器製など、季節や個性に合わせた選択が求められます。 特に警戒心の強い子は、外から中の様子が見える透明な巣箱や、出入り口が大きく開いているものを嫌う傾向があります。 -
巣箱の置き場所:
巣箱をケージ内のどこに置くかも、ハムスターの安心感を左右します。 人の出入りが激しいケージの扉付近や、常に視線を感じる中央部分ではなく、ケージの隅の落ち着ける場所に設置してあげるのが基本です。
これらの点は、飼い主さんが少し工夫するだけで改善できることばかりです。もし心当たりがあれば、まずは巣材の種類をいくつか試してみたり、巣箱のサイズや置き場所を見直したりすることから始めてみてください。
【原因2】実は暑い・寒い?見落としがちな「温度・湿度」の問題
ハムスターは、もともと乾燥した地域の地下に巣穴を掘って暮らしていた動物です。そのため、急激な温度や湿度の変化に非常に弱く、飼育環境の温湿度が不適切な場合、巣作りをやめてしまうことがあります。 これは「巣を作っても快適に眠れない」と感じているサインかもしれません。
-
快適な温度と湿度を知る:
ハムスターにとって快適な環境は、温度が20℃~26℃、湿度が40%~60%の範囲とされています。 この範囲を外れると、ハムスターは体調を崩しやすくなります。特に日本の夏は高温多湿、冬は低温乾燥となりがちなので、年間を通じた管理が欠かせません。まずはケージの中、ハムスターが実際に生活する高さに温湿度計を設置し、現状を正確に把握することから始めましょう。 -
暑い場合のサインと対策:
室温が26℃を超えてくると、ハムスターは熱中症のリスクに晒されます。巣箱の中は熱がこもりやすいため、巣作りをやめて涼しい場所を探すようになります。例えば、ケージの隅で体を伸ばして寝ていたり、給水ボトルの近くや陶器製のトイレでぐったりしている場合は、暑さを感じているサインです。 このような時は、エアコンを使用して部屋全体の温度を24℃前後に保つのが最も効果的です。 扇風機の風を直接当てるのはストレスになるため避けましょう。 補助的に、大理石やアルミ製の冷却プレートを置いたり、通気性の良い巣箱に変えたりするのも良い方法です。 -
寒い場合のサインと対策:
逆に温度が10℃を下回るような環境では、ハムスターは「疑似冬眠」という危険な状態に陥ることがあります。動きが鈍くなり、食欲が落ち、巣箱から出てこずに丸まっているのは寒いサインかもしれません。 対策としては、これもエアコンで部屋全体を暖めるのが基本ですが、ペット用のパネルヒーターをケージの下に敷くのも有効です。ただし、ケージの床全面を暖めてしまうと、ハムスターが暑いと感じた時に逃げ場がなくなってしまうため、必ず床の半分程度に設置するようにしてください。 また、巣材を保温性の高いペーパーチップなどに変え、多めに入れてあげることで、ハムスター自身が暖を取れるように手助けしてあげましょう。
【原因3】騒音や光がストレスに!安心できない「ケージの置き場所」
非常に臆病で警戒心の強いハムスターにとって、「静かで暗いこと」は安心できる環境の絶対条件です。 人間にとっては些細な生活音や光でも、体の小さなハムスターには大きなストレスとなり、巣作りという本能的な行動を妨げる原因になります。
もし、ケージを以下のような場所に置いている場合は、見直しを検討してみてください。
-
テレビやスピーカーの近く:
テレビやオーディオ機器から出る大きな音や振動は、ハムスターにとって予測不能な脅威です。 特に夜行性のハムスターが眠っている日中に、大音量でテレビを見たり音楽を聴いたりする環境は、質の高い休息を奪ってしまいます。 -
ドアの近くや人の往来が激しい場所:
家族が頻繁に通る廊下やドアの開閉が激しい場所は、そのたびに振動や影の動き、空気の流れが起こり、ハムスターを常に緊張状態にさせてしまいます。これでは安心して巣を作り、眠ることはできません。 -
直射日光が当たる窓際や強い照明の近く:
地下で暮らす習性から、ハムスターは強い光が苦手です。直射日光は熱中症の原因になるだけでなく、体内時計を狂わせる原因にもなります。また、夜間も煌々と部屋の明かりがついているような環境では、昼夜の区別がつかなくなり、活動リズムが乱れてしまいます。
理想的なのは、家の隅にある静かで、日中は薄暗く、夜は自然に暗くなるような場所です。もし適切な場所がすぐに見つからない場合は、日中はケージに布をかけて光を遮ってあげるなどの工夫も有効です。 飼い主さんの存在自体がストレスになることもあるため、特に飼い始めでまだ慣れていない時期は、過度に覗き込んだりせず、そっと見守ってあげる距離感も大切です。
【原因4】お迎え直後や高齢、もしかして妊娠?「ライフステージ」の変化
人間の一生に様々なステージがあるように、ハムスターの短い一生にも大きな変化の時期があります。巣作りをしない原因が、こうしたライフステージの変化に伴うものである可能性も考えられます。
-
お迎えしたばかりの時期:
ペットショップから新しいお家にやってきたばかりのハムスターは、環境の激変に対する大きな不安と緊張の中にいます。 周りは知らない匂いや音ばかりで、自分の身を守ることに必死なため、巣作りまで気が回らないことがよくあります。この時期に最も大切なのは「そっとしておくこと」。最低でも1週間は、エサと水の交換など必要最低限のお世話にとどめ、無理に触ろうとしたり、じっと見つめたりするのは避けましょう。ハムスターが「ここは安全な場所だ」と認識すれば、自然と落ち着いて巣作りを始めます。 -
高齢になったことによる変化(老ハム):
ハムスターの寿命は2~3年と短く、1歳半を過ぎるとシニア期(老ハム)に入ります。 高齢になると、人間と同じように体力が衰え、視力や筋力も低下します。 これまでのように熱心に巣材を運んだり、巣を整えたりする作業が億劫になったり、単純にできなくなったりすることがあります。 もし、食欲が落ちたり、動きが緩慢になったりといった他の老化のサインが見られる場合は、巣作りをしなくなったのもその一環かもしれません。 この場合は、飼い主さんが巣作りを手伝ってあげる必要があります。細かく裂いたキッチンペーパーなどを巣箱に多めに入れてあげたり、段差の少ないバリアフリーな環境を整えてあげたりするなど、老ハムが快適に過ごせるようなサポートをしてあげましょう。 -
妊娠の可能性(メスの場合):
もしメスのハムスターで、オスと一緒に飼育していた時期がある場合、妊娠の可能性も考えられます。妊娠中のメスは、出産に向けて非常に神経質になり、巣作りに没頭することが多いですが、個体によってはストレスからか落ち着きがなくなり、巣作りをしなくなるケースもあります。お腹が大きくなる、乳首が目立つようになるといった変化が見られたら、速やかにオスと離し、高栄養の食事と静かな環境を提供してあげてください。
【原因5】見逃さないで!最も注意すべき「病気や体調不良」のサイン
これまで挙げてきたどの原因にも当てはまらず、特に環境を変えたわけでもないのに突然巣作りをしなくなった場合、最も注意深く観察すべきなのが病気や怪我の可能性です。 巣作りは体力を使う行動のため、体のどこかに痛みや不調があると、その余裕がなくなってしまいます。巣作りをしないことに加えて、以下のようなサインが見られたら、迷わず動物病院を受診してください。
- 食欲がない、水を飲まない: 健康の基本バロメーターです。半日以上食べたり飲んだりしていない場合は危険なサインです。
- 元気がない、ぐったりしている: ケージの隅でうずくまって動かない、いつもより活動量が極端に少ない。
- 体重が急に減った: 定期的に体重を測り、急激な減少がないかチェックしましょう。
- 毛並みが悪い、脱毛している: ストレスや皮膚病の可能性があります。
- お尻周りが濡れている・汚れている: 「ウェットテイル」と呼ばれる命に関わる下痢の症状かもしれません。
- 呼吸が速い、苦しそう、変な音がする: 呼吸器系の疾患が疑われます。
- 目やにが出ている、目が開かない: 結膜炎などの目の病気の可能性があります。
- 体を頻繁にかく: 皮膚にダニが寄生していたり、アレルギーを起こしていたりするかもしれません。
ハムスターは、野生では捕食される側の動物であるため、自分の弱みを隠す本能があります。 飼い主さんが気づくほどの症状が出ている時は、病気がかなり進行しているケースも少なくありません。 「いつもと違う」と感じる飼い主さんの直感は非常に重要です。「少し様子を見よう」と自己判断せず、できるだけ早くハムスターの診療が可能な動物病院の専門家に相談しましょう。
| 原因カテゴリ | 具体的な原因 | チェックすべきサイン | 緊急度 | 今すぐできる対策 |
|---|---|---|---|---|
| 環境 | 巣材・巣箱の問題 | 巣材を全く運ばない、巣箱に入らない、巣箱の隅をかじる | ★☆☆ (まずは様子見) | 巣材を数種類用意する、巣箱のサイズ・素材・場所を見直す |
| 環境 | 温度・湿度の不一致 | 体を伸ばして寝ている(暑い)、丸まって動かない(寒い) | ★★☆ (早めに対策) | 温湿度計を設置し、エアコンやヒーターで適正範囲に調整する |
| ストレス | 騒音・光の問題 | 物音に過敏に反応する、飼い主の手から逃げる、ケージを噛む | ★★☆ (早めに対策) | 静かで暗い場所にケージを移動する、日中は布をかける |
| ライフステージ | お迎え直後・高齢化 | 環境に慣れていない様子、動きが緩慢、食が細くなった | ★☆☆ (丁寧な観察) | そっとしておく(お迎え直後)、巣作りを手伝う(高齢) |
| 病気の可能性 | 体調不良・怪我 | 食欲不振、下痢、脱毛、呼吸異常など、普段と違う様子 | ★★★ (要注意・病院へ) | 他の症状がないか全身をチェックし、すぐに動物病院に連絡する |

今日からできる!ハムスターが安心して巣作りできる環境の整え方
ハムスターが巣作りをしない原因に心当たりはありましたか?原因がわかれば、次はいよいよ実践です。ハムスターにとっての「最高のマイホーム」をプレゼントしてあげるのは、決して難しいことではありません。これからご紹介する4つのステップと最後のチェックリストを使えば、まるでプロの建築家になった気分で、あなたのハムスターに理想の住まいを提供できます。大切なのは、完璧を目指すことよりも、愛情を込めて一つひとつ試してみること。もし何から手をつければ良いか迷ったら、一番簡単そうな「ステップ1」から始めてみませんか?
ステップ1:巣材選びの黄金律「組み合わせ」と「深さ」
巣作りの基本となるのが「巣材」です。人間が布団の素材にこだわるように、ハムスターも巣材には好みがあります。最高の寝心地を提供するためのポイントは、「素材の組み合わせ」と「十分な深さ」です。
-
基本の床材とプラスアルファの巣材:
まず、ケージ全体に敷く「床材」を準備します。アレルギーの出にくい広葉樹(ポプラなど)のウッドチップや、保温・吸湿性に優れた紙製のペーパーチップがおすすめです。 [17, 22] これだけでも巣材になりますが、さらにハムスターが自分でカスタマイズできるような「プラスアルファの巣材」をケージの隅に置いてあげましょう。細かく裂いたキッチンペーパー(無香料・無着色)や、市販のハムスター用わたなどが人気です。 [31] ハムスターはこれをせっせと巣箱に運び、自分好みのフカフカなベッドを作り上げます。 -
安全な素材と避けるべき素材:
素材選びで最も重要なのは安全性です。アレルギーを引き起こす可能性がある針葉樹のチップは避けるか、使うなら加熱処理済みの低刺激なものを選びましょう。 [14, 22] また、手芸用の綿や脱脂綿は、ハムスターの足に絡まって壊死させたり、誤って食べて腸閉塞を起こしたりする危険があるため、絶対に使用しないでください。 [21] -
巣作り本能を刺激する「深さ」:
野生のハムスターは地下に穴を掘って暮らす習性があります。 [8, 27] その本能を満たしてあげるために、床材はケチらずにたっぷりと、最低でも3〜5cmの深さまで敷き詰めてあげましょう。 [8] これにより、ハムスターは潜ったり掘ったりする行動ができ、ストレス解消にも繋がります。 [26]
まずは、今使っている床材に加えて、キッチンペーパーを少し入れてあげることから試してみてください。ハムスターが喜んで運ぶ様子が見られるかもしれません。
ステップ2:巣箱はケージ内の「立地」と「間取り」で選ぶ
巣箱はハムスターにとって、外敵から身を守り、安心して眠るための「寝室兼シェルター」です。 [8, 13] 巣箱選びのポイントは、ケージ内のどこに置くかという「立地」と、ハムスターにとって快適な「間取り」(サイズや形状)です。
-
巣箱の最適な「立地」:
巣箱はケージの隅など、壁際で落ち着ける場所に設置するのが基本です。 [1] 人の出入りが激しい扉の近くや、ケージのど真ん中では、ハムスターは常に周囲を警戒してしまい、リラックスできません。 [1, 2] -
快適な「間取り」とは:
巣箱のサイズは、ハムスターが3匹ほど入れるくらいの広さが理想的とされています。 [10] 狭すぎると窮屈ですが、広すぎても落ち着きません。 [8] また、底がないタイプの巣箱は、ハムスターが床材を掘って自分好みの深さに調整でき、掃除もしやすいのでおすすめです。 [7] -
素材ごとのメリット・デメリット:
巣箱の素材にはそれぞれ特徴があります。木製はかじり木にもなり、通気性や保温性に優れますが、おしっこが染み込みやすいのが難点です。 [12] 陶器製は夏はひんやりと涼しく、掃除が簡単ですが、冬は冷えやすいので注意が必要です。 [12] プラスチック製は安価で洗いやすいですが、かじり癖のある子には不向きです。 [12, 13] 季節やハムスターの個性に合わせて選んであげましょう。
巣箱の位置を少し変えるだけでも、ハムスターが急に入ってくれることがあります。ぜひ、ケージの中のベストポジションを探してあげてください。
ステップ3:「ケージ全体」を静かで快適な高級住宅に
いくら素晴らしい巣材と巣箱があっても、家(ケージ)そのものが劣悪な環境では意味がありません。ハムスターが安心して巣作りをするためには、「ケージ全体」の環境、特に温度・湿度と置き場所が極めて重要です。
-
鉄則!温湿度管理:
ハムスターにとって快適なのは、温度20℃~26℃、湿度40%~60%の範囲です。 [3, 5, 6] この範囲を外れると、暑さでぐったりしたり、寒さで危険な疑似冬眠状態に陥ったりします。 [3] まずはケージの近くに温湿度計を設置し、現状を把握しましょう。 [20] -
季節ごとの対策:
夏場や冬場は、エアコンで部屋全体の温度を管理するのが最も安全で効果的です。 [1, 6] エアコンがない場合は、夏は凍らせたペットボトルをタオルで巻いてケージのそばに置いたり、大理石のプレートを入れたり、冬はペット用のパネルヒーターをケージの下に敷く(必ず半分だけにして逃げ場を作ること)などの対策が有効です。扇風機やヒーターの風が直接当たるのは絶対に避けてください。 [4, 11] -
静かで安心できる「ケージの置き場所」:
ハムスターは非常に臆病で、大きな音や振動、強い光が大きなストレスになります。 [24] テレビやスピーカーの近く、ドアの開閉が頻繁な場所、直射日光が当たる窓際などは避けましょう。 [1, 2] 家の中でも比較的静かで、一日を通して明るさが大きく変わらない壁際に、床から少し高い棚の上などに置いてあげるのが理想的です。 [1, 2]
ステップ4:やりすぎ注意!「安心」を残す掃除の作法
清潔な環境は病気予防のために不可欠ですが、過度な掃除はハムスターのストレスになる諸刃の剣です。 [23] なぜなら、ハムスターは自分の匂いがすることで安心感を得る動物だからです。 [32] 巣作りを促すには、「安心できる匂い」を少しだけ残してあげるのが掃除の極意です。
-
全部リセットはNG!匂いを残す工夫:
ケージを丸洗いする大掃除は、月に1〜2回程度で十分です。 [23, 30] その際、古い床材をすべて捨ててしまうのではなく、一握りほど取っておき、新しい床材に混ぜて戻してあげましょう。 [32] これだけで、ハムスターは自分のテリトリーに帰ってきたと安心し、落ち着きを取り戻しやすくなります。 -
巣箱の掃除は慎重に:
巣箱はハムスターにとって最もプライベートな空間です。 [23] ここを頻繁に掃除すると、安心できる場所を奪われたと感じ、巣作りをやめてしまうことがあります。 [23] 明らかに汚れている場合を除き、巣箱の中の掃除はそっとしておいてあげましょう。 -
毎日のプチ掃除で清潔をキープ:
大掃除の頻度を減らす代わりに、毎日の「プチ掃除」を習慣にしましょう。 [30] トイレの砂やおしっこで汚れた床材など、汚れた部分だけを毎日取り除いてあげることで、ケージ全体を清潔に保つことができます。 [28]
総仕上げ:あなたのハムスターは安心して眠れてる?行動チェックリスト
さあ、これまでのステップの総仕上げです。完璧を目指す必要はありません。このリストの中で一つでも「できていなかったな」という項目を見つけ、改善してあげるだけで、あなたのハムスターの住環境は格段に向上します。まずは1つクリアすることを目標に、チェックしてみましょう!
-
巣材 床材が3cm以上の深さで敷かれ、キッチンペーパーなどプラスアルファの巣材がある。 アクション: 床材を補充し、細かく裂いたキッチンペーパーを隅に置く。
-
巣箱 ケージの隅に置かれ、ハムスターが中で体を一回転できる程度の広さがある。 アクション: 巣箱をケージの隅に移動させる。サイズが合わない場合は段ボールで仮の巣箱を作ってみる。
-
温湿度 温度計が20~26℃、湿度計が40~60%の範囲を指している。 [3, 5, 6] アクション: ケージの近くに温湿度計を設置し、エアコンや冷却/保温グッズで調整する。
-
ケージの場所 静かで、直射日光やエアコンの風が当たらず、床から離れた棚の上などにある。 [1, 2, 4] アクション: 静かな部屋の壁際に移動させる。日中はケージに布をかけて光を遮る。
-
掃除 汚れた部分だけ毎日掃除し、大掃除の際は古い床材を少し混ぜている。 [23] アクション: 次の掃除の際、古い床材を一握りだけ残して新しいものに混ぜてあげる。

ただの個性?それとも病気?動物病院へ行くべき症状チェックリスト
環境を整えても、ハムスターが巣作りをしない。そんな時、飼い主さんの心には「もしかして、どこか具合が悪いの?」という、最も大きな不安がよぎります。ハムスターは、野生では捕食される側の動物。そのため、自分の弱みを隠すのが非常にうまく、飼い主が「明らかに様子がおかしい」と気づいた時には、病気がかなり進行しているケースも少なくありません。
もちろん、巣作りをしないのが単なる気分や好みであることもあります。しかし、ハムスターは不調を隠す名人です。だからこそ、飼い主さんが「病気の可能性」を頭の片隅に置き、他のサインがないかを確認してあげることが、彼らの命を救うことに繋がるのです。 これから紹介するチェックリストは、あなたの不安を具体的な観察ポイントに変え、「いつ病院へ行くべきか」を判断するための羅針盤です。多くの項目を挙げますが、全てに当てはまる必要はありません。一つでも「いつもと違う」と感じる点があれば、それが重要なサインです。このリストは、あなたの観察を整理するための道具だと考えてください。
飼い主さんの「いつもと違う」が最重要のサイン
ハムスターの体調不良のサインは、時に非常に些細な変化として現れます。毎日お世話をしている飼い主さんだからこそ気づける「なんとなく元気がない」「食欲が落ちた気がする」といった直感は、どんな高度な医療機器よりも優れた早期発見センサーです。特に、巣作りという本能的な行動をやめてしまうのは、体力を温存しようとしているサインかもしれません。「少し様子を見よう」と判断する前に、まずは体を優しく触ってしこりがないか、お尻は汚れていないかなど、具体的なチェックを始めましょう。
危険度別・受診判断チェックリスト
以下のリストで、ハムスターの様子を客観的にチェックしてみましょう。気になる項目をタップすると、詳細が表示されます。特に「🔴緊急」に当てはまる症状が一つでも見られた場合は、様子を見ずに、すぐにハムスターを診てくれる動物病院に連絡してください。ハムスターの体調変化は非常にスピーディーで、半日〜1日の判断の遅れが命取りになることもあります。
考えられる病気: ウェットテイル(増殖性回腸炎)
飼い主さんがすべきこと: すぐに動物病院へ連絡。保温し、可能なら濡れたお尻を優しく拭く。
考えられる病気: 低体温症、てんかん、重度の衰弱
飼い主さんがすべきこと: すぐに動物病院へ連絡。体を温め、静かな環境を保つ。
考えられる病気: 肺炎、心臓病、呼吸器感染症
飼い主さんがすべきこと: すぐに動物病院へ連絡。ケージ内を適切な温度・湿度に保つ。
考えられる病気: 不正咬合、消化器系の不調、全身の痛み
飼い主さんがすべきこと: 動物病院に連絡して指示を仰ぐ。ふやかしたペレットなどを口元に運んでみる。
考えられる病気: 腫瘍、膿瘍、腹水
飼い主さんがすべきこと: 早めに動物病院を受診。しこりの大きさや場所を記録しておく。
考えられる病気: 皮膚病、アレルギー、栄養失調、ストレス
飼い主さんがすべきこと: 床材などアレルギーの原因になりそうなものを見直し、病院で診察を受ける。
考えられる病気: 不正咬合
飼い主さんがすべきこと: 硬いものを食べづらそうなら病院へ。定期的な歯のカットが必要な場合も。
考えられる病気: 老化、軽度の体調不良、怪我の可能性
飼い主さんがすべきこと: 他に症状がないか注意深く観察。2〜3日続くなら病院に相談。
考えられる病気: 結膜炎、アレルギー、風邪
飼い主さんがすべきこと: ぬるま湯で湿らせたコットンで優しく拭う。改善しないなら病院へ。
迷いは禁物!緊急度MAXの「レッドカード」症状
チェックリストの中でも、特に以下の症状はハムスターからの「命の危険信号」です。これらの症状が見られたら、たとえ夜間や休日であっても、救急対応してくれる動物病院を探して連絡を取ることを強く推奨します。
-
お尻が常に濡れている(ウェットテイル):
これは単なる下痢ではありません。特に若いハムスターに見られ、急激な脱水症状を引き起こし、1〜3日で命を落とすこともある非常に危険な病気です。強烈な臭いを伴うこともあります。 -
ごはん・お水を全く口にしない:
体が小さいハムスターにとって、絶食・絶水は致命的です。24時間以上何も口にしていない場合、深刻な脱水や低血糖に陥っている可能性があります。 -
ぐったりして動かない、または体が冷たい:
ハムスターは寒すぎると疑似冬眠に入ることがありますが、これは本来の冬眠とは違う危険な状態です。体が冷たく、呼びかけにほとんど反応しない場合は、低体温症の可能性があります。
獣医師に何を伝える?「問診準備シート」
いざ動物病院に電話をしたり、診察を受けたりする際、動揺してうまく症状を伝えられないことがあります。事前に以下の情報をメモしておくと、獣医師が迅速かつ的確に診断を下す助けになります。
ハムスターを診てくれる動物病院は限られているため、事前に電話でハムスターの診察が可能か確認しておくとスムーズです。「エキゾチックアニマル診療可」と掲げている病院を探すのも一つの方法です。あなたの迅速な判断と的確な情報提供が、小さな命を救う最大の力になります。
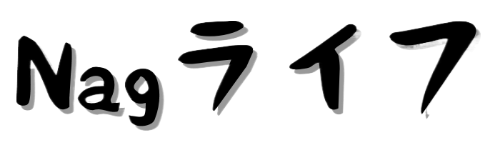

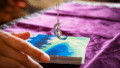
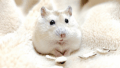
コメント